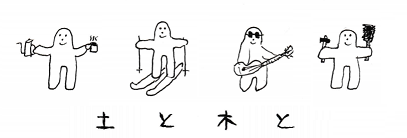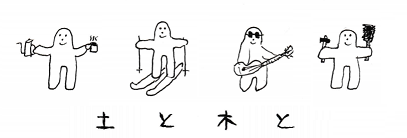|
土と木と便り
|
2023年4月号
|
古くから珈琲文化が親しまれてきたヨーロッパの歴史を掘り下げていくと、焙煎はもともと各家庭の台所仕事でした。生豆を街で買ってきてその日に飲む分だけの豆を台所で煎り、美味しさの三原則「煎りたて挽きたて淹れたて」を当然のように嗜んでいたようです。
次第に産業革命や分業化の流れで人々は忙しさと引き換えに便利さを求めざるを得なくなり、予め焙煎された豆を街で買うようになりました。さらには安さや手軽さを追求してインスタントコーヒーや缶コーヒーのような工業製品的なコーヒーが誕生し、やがて一杯分ずつ個包装されたドリップバッグが流通するようにもなりました。
その反面、品質の低いコーヒーがたくさん出回り、それを覆い隠すかのように業界側からは根拠不明なコーヒーウンチクが流布されたり、自家焙煎コーヒー店からも「スペシャルティ」や「フルーティ」など、いかにも品質の高い生豆を使用しているかのような話が強調されるようになりましたが、しかし最も肝心な焙煎後の煎り豆の品質については特に触れず、賞味期限を製造日から1年後に設定したり、長期間経過して豆が酸化している可能性のあるものを「エイジング」や「熟成豆」と称するなど、残念ながら美味しさの三原則からはかけ離れたものが一般的なものになってしまいました。
それでもやはり珈琲豆は本来貴重な農産物であり生鮮食品なのです。土と木との焙煎はかつてのヨーロッパの家庭のように台所焙煎の延長線上にあるものです。実際に店主は開業するずっと前、生豆を入手しては台所で小さな手鍋を振って焙煎をしていました。それがやがて一度に200g焼ける小型の手回し焙煎機に代わり、当時は酪農家でしたが、仕事後に夜な夜な立ったまま眠りそうになりながらよく豆を焼いていました。珈琲豆屋として開業した今、焙煎機はその当時よりも大きなものになりましたが、相変わらず手回し焙煎です。
何よりも「煎りたて」の美味しさを大切にしていこうというスタンスは開業当初から一貫しているので、いつも煎りたてになるように少量ずつ焙煎し、ドリップバッグのような二次加工品は決して製造販売しません。
ドリップバッグは品質の低下に加え個包装ゆえに、たった一杯の珈琲を飲むためだけにたくさんのゴミを出してしまうことについてもやはりいかがなものかと思います。そういったものは作る側も買う側も自らの意思で選択しないようにすれば、やがて出回ること自体なくなります。
台所で焼いた豆をその場で挽いて淹れて飲む…そんなシンプルで最も美味しい珈琲の飲み方をなるべくそのままお届けする、それが土と木との珈琲です。
|